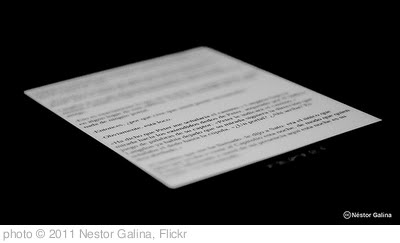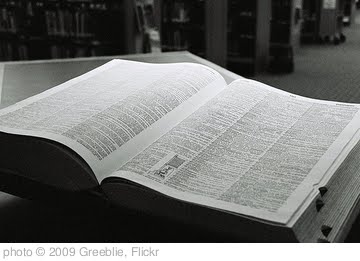2010年、電子書籍元年と言われました。1年経て注目のフォーマットEPUBの議論もだいぶと目にするようになってきました。しかし、依然としてまとまらないような気がしてなりません。
見えてくるのはフォーマットやリーダの乱立した混戦模様。国内の群雄割拠ぶりはこちらの電子書籍情報まとめノートさんのエントリに詳しいですが、多分このまままとまらないであろうこと、そしてまた5年後か10年後かに「今年こそは電子書籍元年だ」って同じように言ってるんだろうなぁという将来が容易に想像できます。シグマブックやWordsGear、リブリエのように歴史はやっぱり繰り返すのです。
最近は特にEPUBの議論を目にしたりするのですが、どうしても違和感を感じてなりません。EPUBでなきゃいけない理由が無いんじゃないかというのが僕の主張。
例えば、EPUBを始めとする電子書籍のメリットとしてリフローである(文字の大きさや画面の大きさに合わせて表示が柔軟に変え得ることの意味)ことが必ず出てきますが、その一方で、ページの考え方をどうするか懸念していたり、CSSはリーダによって解釈に違いがあり過ぎるから意図した見た目にするのが大変だねどうしよう、って議論があったりします。
他にも EPUB3 の前に散々議論されてましたが、ルビとか縦書きって話も同様ですね。禁則とか圏点とかもそうですかね。やっぱり見た目は大事なんですよ。「如何に紙への印刷と同じものが再現できるかが重要」なんてコメントも耳にしたりしますしね。そりゃそうです、見せる(魅せる)為の編集だし出版なのですから。だからどこまでいっても意図した通りに見せたい思いは必ずあって、結局WYSIWYGなのだと思うのです。
他にも例えばこういう記事もあります。
見開き表示に対応したEPUB形式の電子書籍を日本で初めて制作し提供を開始 - Apple独自の拡張仕様を活用し『JAZZ JAPAN』で紙の雑誌レイアウトを再現 -
固定レイアウトなEPUBなんて言葉が出てくると、もう何の為のEPUBか分からなくなってしまいます。リフローが良くて始めたEPUBなのに、レイアウトが重要だから固定してみました的な。じゃぁ、
何でPDFじゃダメなんでしょうか。

EPUBを論ずるときにレイアウトが検討事項として存在し、そのどこかに WYSIWYG 的考えが少しでもあるなら、誰がどう考えてもPDFに軍配があがります。Adobeに言わせれば ISO にまでなってるPDFを舐めるなっ!てモンじゃないでしょうかね、ホント。(まぁそんなAdobeもInDesignで早くからEPUB出力できる事をPRしていたりするのでよく分からないですが)
PDFには「全ての環境においてほぼ同様の状態で文章や画像を閲覧できるようにする」というミッションのもと1993年から地道に積み上げられてきた歴史があります。なので、書籍や雑誌というメタファーが大事で且つ見た目という要素が検討項目に入っている時点で、PDFからの脱却は考えない方が良いと思うんですよね。あるいは、コミック系の自炊でよく使われている jpeg 画像をzipで固めただけの ZIP BOOK 形式ぐらいに割り切ってしまうぐらいの勢いとか。だって、見た目が重要なんですから。
一方PDFではダメという根拠に、段組のコンテンツがiPhone等のスマートフォンでは読み難いという主張もあったりしますが、果たしてそうでしょうか。
こういう技術(工夫)も含めて読み易くする為の仕掛けはある訳です。段組→小さい→読みにくいはちょっと短絡的な発想じゃないかなと思います。アプリケーション層での見せ方の工夫をせずに、コンテンツの作り方まで手を入れようとするのは果たして合理的な選択なのか。
もしiPhoneで読み難い事を解消する為にフォントサイズ変更が自由なリフローという選択肢を取るのなら、レイアウトは犠牲にすべきなのは皆さん薄々気付いている筈なんですよね。だって、EPUBのコア技術はhtml+cssであり、webの世界でレイアウトが紙のような再現度を持ってない事は自明な訳ですから。

webにはwebで意図通りの見た目を実現するテクニックが様々醸成されて来た歴史もありますから、それを使う手もあるとは思います。html+cssなwebをマルっとzip化したweb魚拓+アルファな考え方ですね。スマートフォンやタブレット型端末に特化するならWebKitに最適化する事で概ねカバー出来るのでやり易い筈です。ちなみにAppleは MacOSX Safariの .webarchive という保存形式でそれを実現していて、iOS上ではUIWebViewに webarchive を食わせるとそのままWebスナップショット的に表示してくれたりもします。
まぁ色々書いていますが何が言いたいかというと、PDF なり jpeg なり webarchive なり、レイアウトや見た目を保持する技術は既に確立されているのに、何でわざわざ新しいフォーマットに飛び込んでレイアウトの議論に苦心されてるのだろう?ってこと。ここが凄く違和感なんですよね。
もちろん、リフロー以外にEPUBのメリット(とされるモノ)は沢山あります。でも、EPUBでなきゃほんとにダメかって感じで、決定打が無くやっぱり違和感があるのは否めません。
|
索引や栞や目次
|
PDFでも存在する
|
|
作者等のメタデータ
|
PDFでも存在する
|
|
リッチ化
|
PDFで既に実現している(画像はもちろんのこと、movieやsoundが埋め込めたり js が埋め込めるのはよく知られた事実。jsはPDF1.3以降、リッチコンテンツはPDF1.5以降)
|
|
著作権保護(DRM)
|
そもそもコンテンツのフォーマットに内包されるべきではない。実装に依存させた別の技術とするべきだし、EPUBでは実際出版社もそれぞれ独自に行うつもりとされている
|
|
閲覧権制御(こちらもDRM)
|
AdobeがLiveCycleで実現している(ただLCを使うとオフライン読書体験は犠牲になる…のと極めて高価)
|
|
パッケージング
|
PDFはそもそもコンテンツを1つのファイルとしてパッケージングするコンテナフォーマットである
|
こんな風に。ほとんどはPDFで実現されているんです。何でそれをイチから作りなおそうとするのか?それが幾ら考えても分かりません。加えてPDFには、改竄されていない事を証明したり有効性証明をする為の ISO30000-2 ISO32000-2 として採用手続き中のタイムスタンプという機能もあります。EPUBではそこまでの考慮は無い。
確かにEPUBでしか規定できない情報もあるでしょう。でも、それの為にコンテンツの作り方まで根こそぎ変えようっていうのはどうかと思うのです。僕はPDF最強だと考えてまして、そんなにややこしい議論するならもう媒体はPDFで良いじゃんっていつも感じてしまいます。ページという存在、書籍や雑誌というパッケージングの存在がそれほど重要なら多分、PDF+アルファで良い。その上でもし電子書籍を論ずるのであれば、その論点は、電子化の新しい手法や仕様ではなく、
- PDFを如何にリッチにするか
- PDFを如何に読みやすくするか
- PDFを如何に管理し易くするか
- PDFを使って如何に新たな読書体験へと読者を誘(いざな)うか
という事にしたらどうかと思うのですよね。(既に1.はPDFの仕様が結構内包してますが)
開発者が一番嫌う事に車輪の再発明というモノがあります。既にプログラムがあるのに同じモノを作るだけの自己満足を揶揄する表現です。無論、自己学習の為に敢えて同じものを作る事はあったりしますが、あくまで勉強用途に限られています。何だか…EPUBの議論って開発の世界で言うところの車輪の再発明をしようとしている風に見えて仕方が無いのです。
電子書籍フォーマット「EPUB 3」ってぶっちゃけどうよ?
この記事を「で、PDFではダメなの?」という視点で読んで頂くと興味深いのですが、やっぱりEPUBでなければならない理由って出てこないんですよね。
それでも、この記事が言うようにフォーマットの是非は関係なくEPUBという新しいフォーマットの誕生が電子書籍業界に活気を与えるという理由等でやっぱりEPUBだという事であれば、やはり紙とページの概念は捨てるべきだと僕は思ってます。OPS(EPUB3では EPUB Content Documents 3.0となる)で文書構造が明示的に書かれる事になるのに、何で読み手の読書体験を分断する「ページ」という余計な区切りを取り込む必要があるんでしょう。元は html+css なのだから、web 的な読ませ方を想定するべきじゃないでしょうか。やはり「ページ」が必要なら繰り返しになりますがPDFで良いんです。ウィンドウの縦解像度に依存して無理やりpagingされるウェブサイト(html+css)って読み易いでしょうか?
読書が好きなので電子書籍は凄く興味あるテーマですが、どこか「書籍の電子化」ばかりを議論しているようで、電子化する事によるメリット(上述の件)の議論が置き去りになっている気がして残念でなりません。誤解を恐れずに書かせて頂くと、昨今の議論は電子書籍化ではなく単なる書籍電子化の再論に過ぎないのではないかと思います。フォーマットって別に読み手には関係無いんですよね。
上述の電子書籍の論点については自分なりのアイディアも一応持っていたりするのですが、今回のエントリがちょっと長過ぎたのでそれはまた別の機会に書いてみたいと思います。