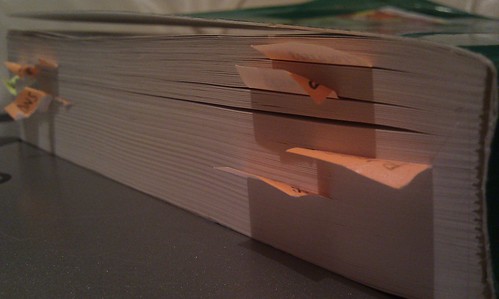仕事柄、企業さんがまとまった数でiPadを導入される事例はwatchしています。今後は情報収集中に見つけた事例をこのブログでもシェアするようにしたいと思います。今回はこちら。
同社は、「iPad」による情報提供活動の実施可能性を検証するため、2010年から3回のトライアルを実施し、良好な結果が得られたことから、「iPad2」1750台を全MR・MAに導入することを決めた。
最近ではちょっと大きめの話かも。MR(Medical Representativeの略)ってのは製薬業界の営業職の方ですから、つまるところiPadを営業支援の為に1750台。綺麗なのか綺麗でないのか微妙な数字ですが、まぁざっと2000台ですから凄い数ですね。
決まるまでに相当な期間を要したと思われますが、いざ入るとなるとこの規模感。エンタープライズが面白いと僕が思う理由はここにあります。iPadがライフスタイルを変えたのであれば、これだけの規模で企業に入ると企業のワークスタイルが変わるって事なんですよね。企業のスタイルが変わるってそうそうありませんから面白い。
中外製薬はPDF閲覧、動画、HTML5で書かれたアプリなどをコンテンツとして閲覧するのだそう。コンテンツ・ドキュメントの類を閲覧するのはもはやタブレット端末に置き換わっていくのは時代の流れだと思います。コンテンツ・ドキュメントを「作る」のは、パソコンであり続けるでしょうけど。
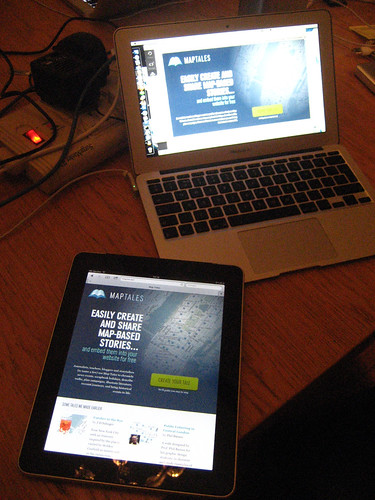
一度にドーンと2000台というパターンは稀ですが、5台→50台→500台→5000台って感じの段階的展開が徐々に始まってるのが2011年だったと言えると思います。来年はドドンと数百台規模での導入なんて話が今年以上に見られるんじゃないかなと。
ちなみに、弊社のiPadビジネス活用を支援するドキュメント共有ソリューション「SYNCNEL」も、同じ市場を見ています。実際この台数以上の4桁台数で契約頂いているお客様もいらっしゃいますので、この規模もどんどん広げていきたいところですね。運用可能なシステムである事は実証出来ていますので。
そんな訳で2011年も師走となりましたが、来年以降はエンタープライズ向けのタブレット市場はますます盛り上がりを見せてくるに違いありません。楽しみです。