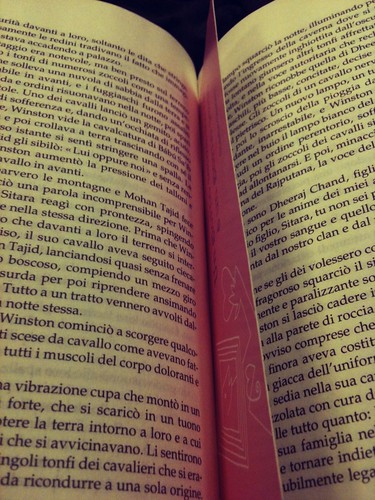サラリーマン時代に研修という名の座学に参加させられる度に思った事があります。
行くべき人はもっと他にいるんちゃうか?
その人とは、当時の自分に言わせればマネージャであったり社長等の経営者であったりしました。人や組織をマネージする人ほど勉強しまくって成長しなくちゃいけない筈なのに、いざその立ち位置に立つと「部下の成長がグループや会社の成長に必要不可欠である」という命題のみに目が行ってしまうものなのかも知れません。(命題としては正しいがそれだけではダメ)
僕は代表の器が組織の器ではないかと考えています。
器の大小が儲けの大小なのか仕事の楽しさ具合なのか、それは組織それぞれに違うのかも知れませんが、その大小を決めるのは代表者の器です。企業は社長を越えられない。同様にグループだってマネージャを越える事は出来ない。組織を代表する人が社長でありリーダでありマネージャな訳ですから、非常に分かり易い真理です。

仮に企業における「器」を「富の量」だとすれば、社長の成長は企業が生み出す富の量を大きく左右する筈です。
成長とは、それは知見を深める事かも知れないし、色んな体験をする事かも知れないし、人間力を高める事かも知れないし、様々あるでしょう。何であれその積み重ねが企業の器を規定し、そこから利する従業員を始めとする関係者(取引先も含む)の幸せ具合も決めてしまうのだと思います。
だから代表者は組織の器を大きくする為に学び成長し続けなければなりません。自分のため、家族のため、スタッフのため、取引先のため、そのほか利害関係者全てのために。マネージャがメンバーよりも勉強していないとか、有ってはならないのでしょう。人の上に立つ以上、1秒1秒の時の刻みの中に学びが常に伴っていなければならないのです。

そんな事を自戒を込めてつらつらと経営ノートを綴っていたら、アッという間に夕方を迎えた秋の日曜日でした。
学び方や成長の仕方は人それぞれかも知れませんが、僕の場合は読書だったりセミナーだったり人と会って話す事だったりします。相変わらず本は読みまくってる方だと思いますが、今週は、かつてビジネスを共にした、とある冒険家の半日セミナーに参加していつもと違う学びを得てくる予定です。

ご一緒される方、宜しくお願い致します。