経営者になってから、正月休み・GW・盆休みなど、まとまった休みの時に色んな事を考えるようになりました。今日は弊社的…というか僕的な組織論の中核を成す人材論もとい人財論…というとちょっと大げさですが、何かにつけ思い巡らす時にベースとなる考え方の一つを書いてみたいと思います。
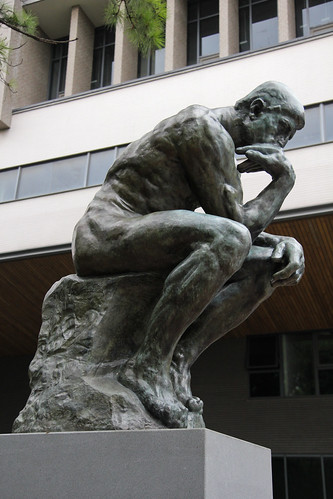
サラリーマン時代、人の頭脳が価値創出機であるITの世界にずっといたからか、知的生産産業における価値創出性能の最大化というテーマに興味を持ち続けてきました。工場等にあるような工員を増やす又は機械への置き換えでないと生産性がスケールしにくい産業に比べて、知的生産産業では頭脳依存つまり個人能力依存が高いぶん生産性がビックリするぐらいに高まる可能性を持っている不可思議感があって面白いからです。
特にITは知への依存度が極めて高いんですよね。ほぼ100%と言っても良いでしょう。そのMAXな不透明感がメチャクチャ面白い。もう全く読めないんですよね。

工場であればラインがあって人がいて機械があって、ラインと作業工程の数が分かれば一日に生み出す生産量って計算でほぼ出てしまいますが、知的生産産業においてはラインに乗るものは知的タスクであり、OUTPUTされるまでの過程の大半が人の頭脳に依っているので厳密に計算出来ません。
知の依存度がMAXなITの場合そのブラックボックス感が半端無くて面白いという事なんです。タスクは瞬殺されるかも知れないし、1つ入れたタスクが期待してた1に対して10の成果物が出てくるかも知れない訳です。もうホント訳わかんない(笑)。面白いじゃないですか。
頭脳、言い換えれば「人」が凄ければ想像を越えた生産性を発揮するかも知れません。更に、人は良くも悪くも外的/内的要因によって生産性が上下しますから「環境」によってはこれまた凄い生産性が獲得できるかも知れません。まさにブラックボックス。それで、
最高の環境と最強の人材が生産性を最大化する
なんて事を僕はよく言うんですが、「環境」と「人材」次第で想像を越えた生産性が実現出来るんじゃないかと思ってて、それを慎重に選んで/整えていく事が経営者の役割の一つだと考えています。生産性を最大化する為に。物凄く当たり前の事なんですけどね、でもこれを執念深いぐらいにやってる企業って余り無い。

知的生産産業の世の中ではいつまでたっても良くも悪くもありがちな就労「環境」が蔓延(はびこ)っているように見えますし、人の生産性を考慮していない「人月」という単位に未だに疑いを持っていないようにも見えますし、工場的発想で安易に人を増やせば生産性も上がると勘違いをしているように見える人もいます。1+1が-1になる可能性もあるというのに。
そうじゃないでしょうと。知的な生産がそんな単純な訳ないでしょうと。
環境が悪ければ1は1だし1年経っても1のままですが、環境が良ければ1は2にも3にもなるし1年経てば5にもなります。その可能性を僕は信じているし、実際にそう。だから、以前にもちょっと書いた事がありますが僕は「環境」には物凄い神経質になっていて、「人材」についてはその「環境」が最大限に作用する人を選んでいます。繰り返しになりますが、執念でしょうね、多分。
「環境は用意しました。あなたがフルタイムで開発に専念したら何が起こるか僕は見てみたい」
というスタンスが基本あります。無論、環境について100%はなくてウチはまだ7割程度しか達成出来ていないと思っていますが、今のところ相当(開発者にとって)環境が良いIT企業の部類には入っているという自負はあります。
「最高の環境と最強の人材が融合したら何が起こるのか。生産性が最大化するに違いない」
…ある意味でこの持論を試す社会実験とも言える僕の組織運営は、初めての増員をしてからの3年間で持論をある程度実証出来ていると感じています。3年で75を数えるアプリを外注さんほぼ皆無で開発している事や、鬼門であるPDFビュワーを多数の既存ビュワーに半年でほぼ追いついている事や、企業向けのシステムにおいては1年で100以上の機能追加をして関係者を驚かせている事などなどを、エンジニアの2011年残業時間合計が5時間越えずに実現出来ているのはその証左でしょう。
ただ、生産性が最大化したから膨大な利益が自然に湧いてくるかというとそこはまた別の話。

(Monetizabilityは超造語ですがw)
創り出す「性能」が前置きとしてあって、そこに価値創出率が最大化するハコを通して初めてマネタイズされる訳です。そのハコが重要で、ビジネスを考える役割も担う経営者だったり企画・マーケ担当が用意しなくてはいけなかったりする所で、時代の潮流にあった新しい技術やアイディア・企画、それを売る為の仕掛けだったりすると考えています。僕はここに、売上高だけを追求するモノではなく、流行り廃れの激しいモノでもなく、継続性も利益率もいずれも高いビジネスを持ってきたいと常々思って来ました。それは凄く難しい事ですけどね。
って、ちょっと横道にそれて長文化しそうなのでこのへんで。
とにもかくにも「最高の環境と最強の人材が生産性を最大化する」ってのが僕の持論。2011年まではこれを実証するフェーズとして動いてきたって感じなのだと思います。もちろん「環境」と「人材」を引き続き追い求めますが、それ以上に2012年以降は「金」という形に転換する部分にも手を入れて、生産性の最大化を経済的対価(つまり金)の最大化に繋げるフェーズに入っていきたいと思っています。
■ 弊社環境について書いたエントリ ■











